地域密着のホームドクターとして35年
当院は予約制で診察を行っています。
- 緊急の際は
お電話ください - 044-433-2274

川崎市中原区の飼い主のみなさま、こんにちは。
武蔵小杉駅からすぐの池田動物病院です。
愛犬が最近、水をたくさん飲むようになったり、毛が抜けてきたりしていませんか?
それはクッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)の初期症状かもしれません。
クッシング症候群はホルモン異常による慢性疾患で、放置すると糖尿病・高血圧・免疫力低下を引き起こし、命に関わる可能性もあります。
特に7歳以上のわんちゃんでは発症リスクが高いため、早めの診断と治療が重要です。
この記事では、クッシング症候群の原因・症状・診断・治療法について解説いたします。

クッシング症候群とは、わんちゃんの体内でコルチゾールというホルモンが過剰に分泌される病気です。
コルチゾールは、ストレスに対処したり、血糖値を調整したりする重要なホルモンですが、過剰になると身体に悪影響を及ぼします。
特に7歳以上の高齢犬(シニア犬)に多く見られ、放置すると糖尿病・高血圧・免疫力低下などの深刻な合併症を引き起こすこともあります。
クッシング症候群には、大きく 3つのタイプ があります。
○原因
脳の下垂体(脳の一部)にできる腫瘍が原因で、副腎を刺激されすぎてコルチゾールが過剰に分泌します。
○特徴
全体の約80~85%のわんちゃんがこのタイプに分類されます。
○主に影響を受ける犬種
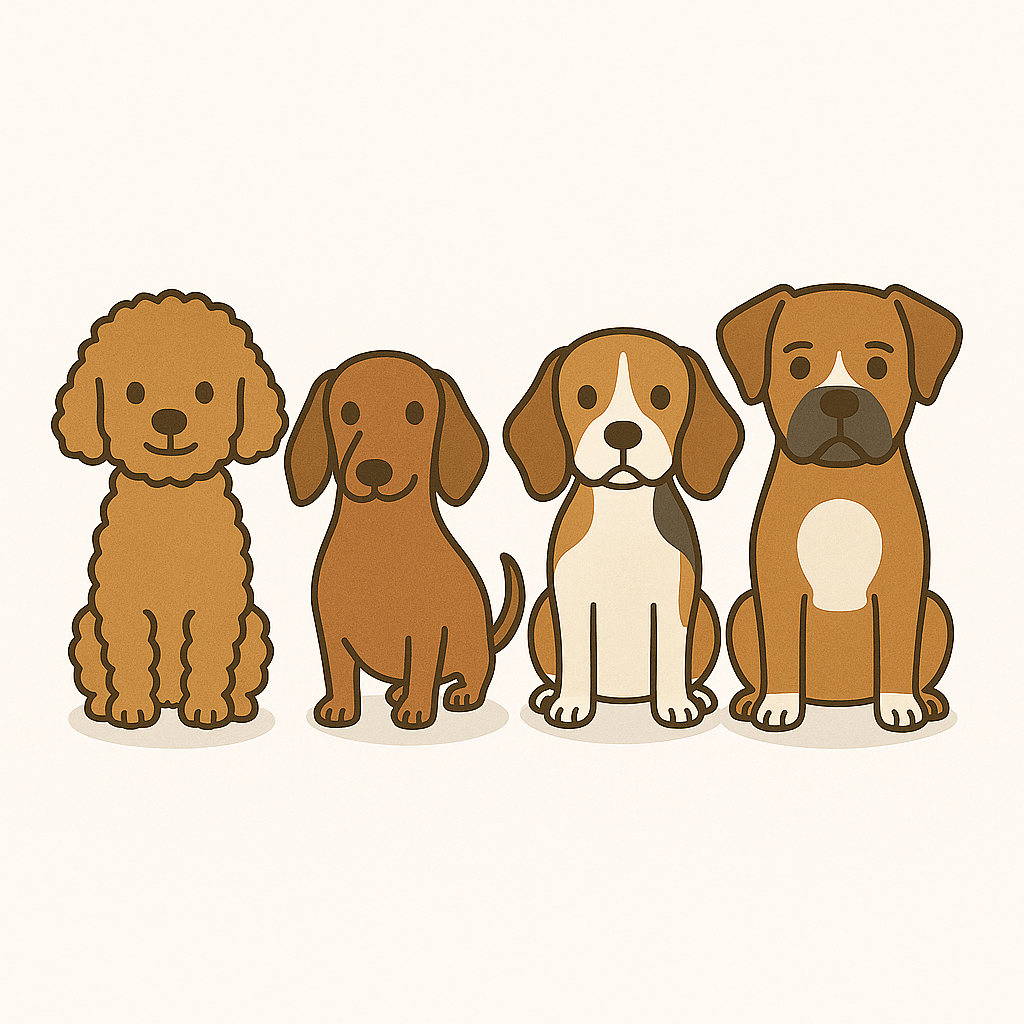
○原因
副腎にできた腫瘍がコルチゾールを過剰に分泌します。
○特徴
全体の約15~20%のわんちゃんが該当します。
手術での摘出が可能なケースが多いです。
○主に影響を受ける犬種
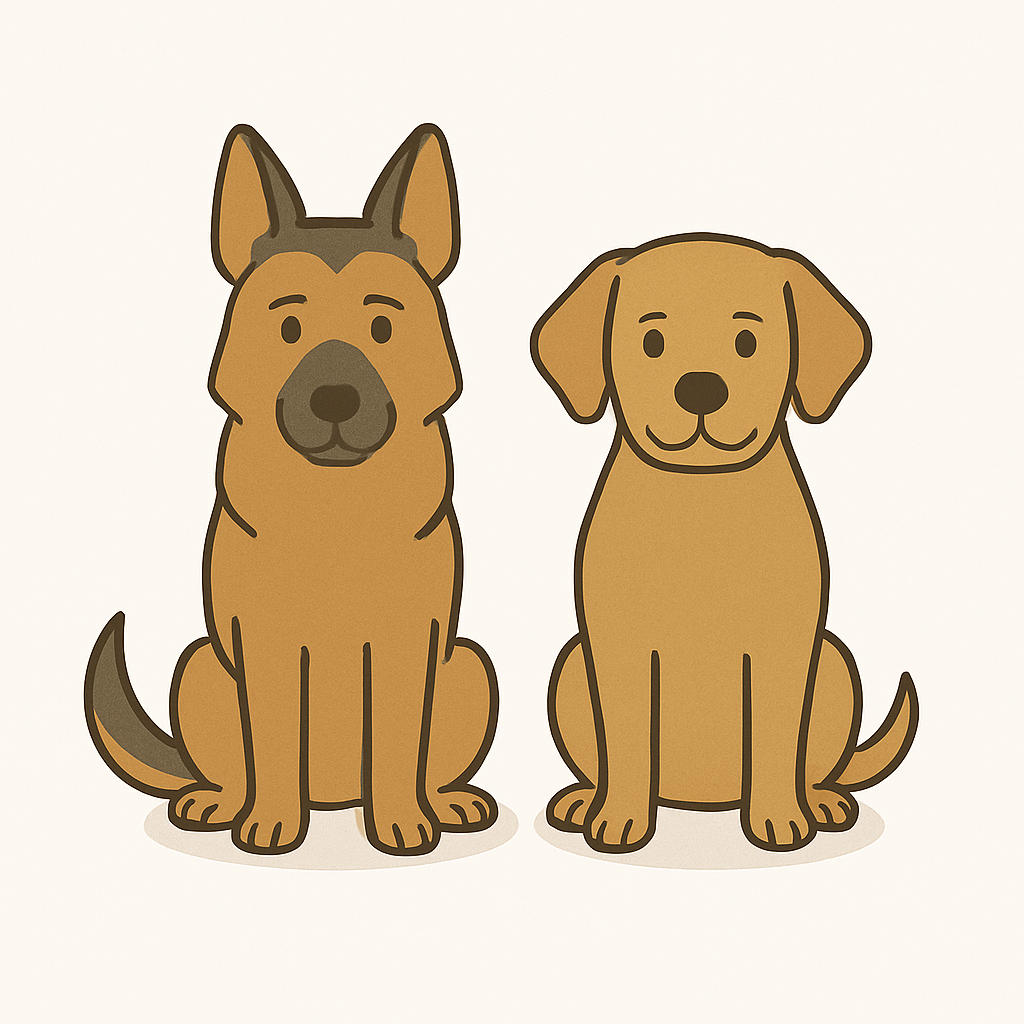
○原因
長期間のステロイド投与による副作用で発症してしてしまいます(人工的にコルチゾールが過剰)。
○特徴
ステロイド薬の適切な調整によって改善が可能。
クッシング症候群の発症要因として、以下のようなものが挙げられます。
下垂体や副腎の腫瘍によるホルモン異常が、クッシング症候群の主な原因です。
特に7歳以上の高齢犬(シニア犬)での発症が多く見られます。
皮膚病や炎症の治療で長期間ステロイド薬を使用しているわんちゃんは、クッシング症候群を発症しやすくなります。
これを医原性クッシング症候群と呼びます。
特定の犬種はクッシング症候群になりやすい傾向があります。
特にプードル、ダックスフンド、ビーグル、ボクサーなどはリスクが高いとされています。
クッシング症候群はゆっくり進行する病気のため、初期症状が年齢による変化と勘違いされることがあります。
しかし、以下のような特徴的な症状が見られたら要注意です。
※1つでも当てはまる場合は、すぐに動物病院を受診しましょう。
クッシング症候群の診断には、いくつかの検査を組み合わせて行うのが一般的です。
コルチゾール値を測定し、異常がないかを確認します。
ACTHというホルモンを注射し、副腎の反応を調べます。
ステロイド(デキサメタゾン)を投与し、コルチゾールの分泌抑制の有無をチェックします。
副腎の大きさや腫瘍の有無、石灰化していないかをチェックします。
他の病気(糖尿病や肝臓疾患)の除外診断のために尿検査を行うことがあります。

下垂体や副腎の腫瘍を詳細に調べるために行うこともあります。
クッシング症候群の治療は、原因に応じて最適な方法を選択します。
トリロスタン(Vetoryl)やミトタン(Lysodren)などの薬を使用し、副腎の働きを抑えます。
副腎腫瘍が原因の場合、外科手術で腫瘍を摘出する方法もあります。
ただし、手術のリスクもあるため、慎重な判断が必要です。
下垂体性クッシング症候群では、放射線治療が有効なケースもあります。
当院では専門的な診断のうえ、最適な治療法をご提案します。
ステロイド薬の投与量を調整することで改善するケースが多いです。
クッシング症候群は進行がゆっくりなため、発見が遅れがちです。
しかし、放置すると糖尿病や免疫低下を引き起こし、命に関わることもあります。
「水をよく飲む」「毛が薄くなる」「おなかが膨らむ」などの症状が見られたら、すぐに動物病院を受診しましょう。
わんちゃんのクッシング症候群は、早期発見・早期治療が鍵となる病気です。
もしかして、うちの子クッシングかも…と思ったら、お気軽にご相談ください。
菊地(さ)愛玩動物看護士
ペンギンが好きです。ジェンツーペンギンも好きですが、アデリーペンギンが一番のお気に入りです。
IKEDA ANIMAL HOSPITAL
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休診 |
| 16:00〜19:00 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● |
提携しているわけではありません。来院前に必ず電話でのご連絡をお願いいたします。
〒211-0002 神奈川県川崎市中原区
上丸子山王町2-1328