地域密着のホームドクターとして35年
当院は予約制で診察を行っています。
- 緊急の際は
お電話ください - 044-433-2274

川崎市中原区の飼い主のみなさま、こんにちは。
武蔵小杉駅からすぐの池田動物病院です。
最近、シニア期に入ったわんちゃんが
「夜に急に吠えるようになった」
「名前を呼んでも反応がない」
「部屋の中をグルグル歩き続けている」
などのご相談が増えています。
こうした行動は、老犬の認知症(認知機能不全症候群)のサインかもしれません。
わんちゃんが年齢を重ねるにつれて、身体の不調だけでなく、脳の機能にも変化が起こります。
西洋医学ではサプリやお薬で対応する方法もありますが、東洋医学の視点を取り入れたケアで、よりやさしく穏やかなサポートができることをご存じでしょうか?
この記事では、老犬の認知症に対する東洋医学的な考え方や、実際に取り入れやすい漢方・養生の方法を、動物病院の視点からわかりやすくご紹介します。
わんちゃんとご家族が少しでも安心して過ごせるよう、ぜひ参考になさってください。

シニア期に入ったわんちゃんに、こんな様子はありませんか?
こうした行動は、老犬の認知症(認知機能不全症候群/Cognitive Dysfunction Syndrome)のサインかもしれません。

認知症のわんちゃんには、以下のような症状が見られます。
進行すると、生活の質(QOL)が大きく低下し、ご家族の介護負担も増えていきます。
小型犬では10歳以上、大型犬では8歳以上あたりから発症リスクが高まります。
特定の犬種(トイプードル、柴犬、ミニチュアダックスなど)での報告もありますが、どの犬種にも起こりうる問題です。
サプリメントや処方薬など西洋医学的なアプローチもありますが、進行を完全に止めることは難しいのが現状です。
そのため「穏やかな時間を長く保つ」「生活の質を少しでも上げる」ことを目指すケアが大切です。
西洋医学に加えて、東洋医学の知恵を取り入れることで、よりやさしい認知症ケアが可能になります。
東洋医学では、老犬の認知症は以下のような身体のバランスの乱れが関係していると考えられます。
東洋医学では「気・血・水(き・けつ・すい)」という3つの要素のバランスが健康を保つカギです。
このバランスが崩れることで、認知症のような症状が現れるとされています。
東洋医学は「体質」や「生活習慣」に合わせたやさしいアプローチが特徴です。
急激な変化を避けたいシニア期のわんちゃんにとって、負担の少ないケア方法として注目されています。
東洋医学的な治療の柱のひとつに、漢方薬の使用があります。
わんちゃんの身体の状態を確認して、漢方を処方します。
当院では、イスクラ社の動物用漢方薬を中心に、安全性の高いものを使用しています。
使用時の注意点
ご自宅でも取り入れやすい、東洋医学的なケア方法=「養生」をご紹介します。
※栄養バランスやアレルギーを考慮しながら取り入れましょう。

当院では、西洋医学だけでなく、東洋医学を取り入れた認知症ケアを行っています。
東洋医学と西洋医学を組み合わせて、その子に合ったオーダーメイドケアをご提案しています。
東洋医学の診療は、名取獣医師が担当いたします。
初診の方は、お電話(044-433-2274)でのご予約をお願いいたします。
鍼治療に関しては、2回目以降もお電話か窓口でのご予約のみとなります。
老化現象と見過ごしがちな症状も、早期に気づくことで対策が可能になります。
「最近ちょっとおかしいかも…」と感じたら、早めにご相談ください。
わんちゃんにとって、毎日を安心して過ごせる環境づくりはとても大切です。
東洋医学をうまく取り入れながら、シニア期の暮らしをより穏やかに、豊かにしていきましょう。
川崎市中原区・武蔵小杉駅近くの池田動物病院では、東洋医学に力を入れたシニア犬のサポートを行っています。
夜鳴きや徘徊などでお困りの飼い主さま、ぜひ一度ご相談ください。
東洋医学の診療は、名取獣医師が担当いたします。
初診の方は、お電話(044-433-2274)でのご予約をお願いいたします。
鍼治療に関しては、2回目以降もお電話か窓口でのご予約のみとなります。
この記事の執筆・監修
執筆:菊地(さ) 愛玩動物看護師
監修:名取 獣医師
菊地(さ)愛玩動物看護師
ペンギンが好きです。ジェンツーペンギンも好きですが、アデリーペンギンが一番のお気に入りです。
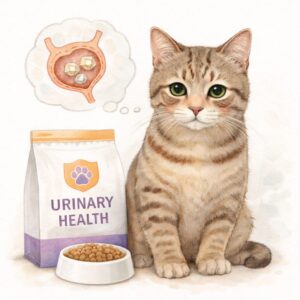


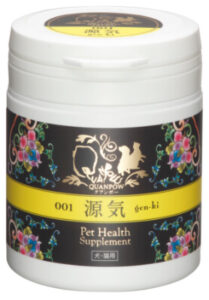




IKEDA ANIMAL HOSPITAL
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休診 |
| 16:00〜19:00 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● |
提携しているわけではありません。来院前に必ず電話でのご連絡をお願いいたします。
〒211-0002 神奈川県川崎市中原区
上丸子山王町2-1328
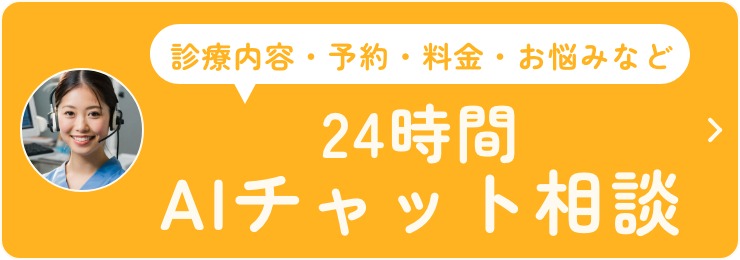
診療内容・予約・料金・お悩みなど
お気軽にご相談下さい
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休診 |
| 16:00〜19:00 | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● |